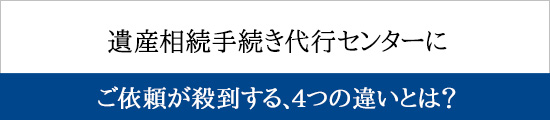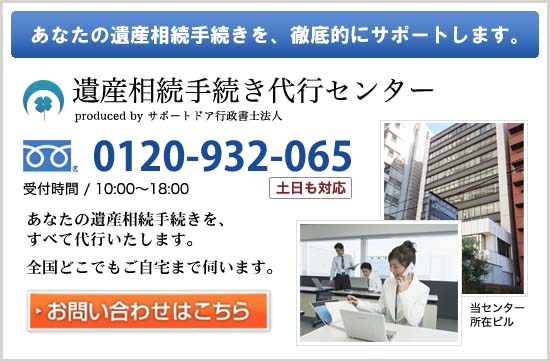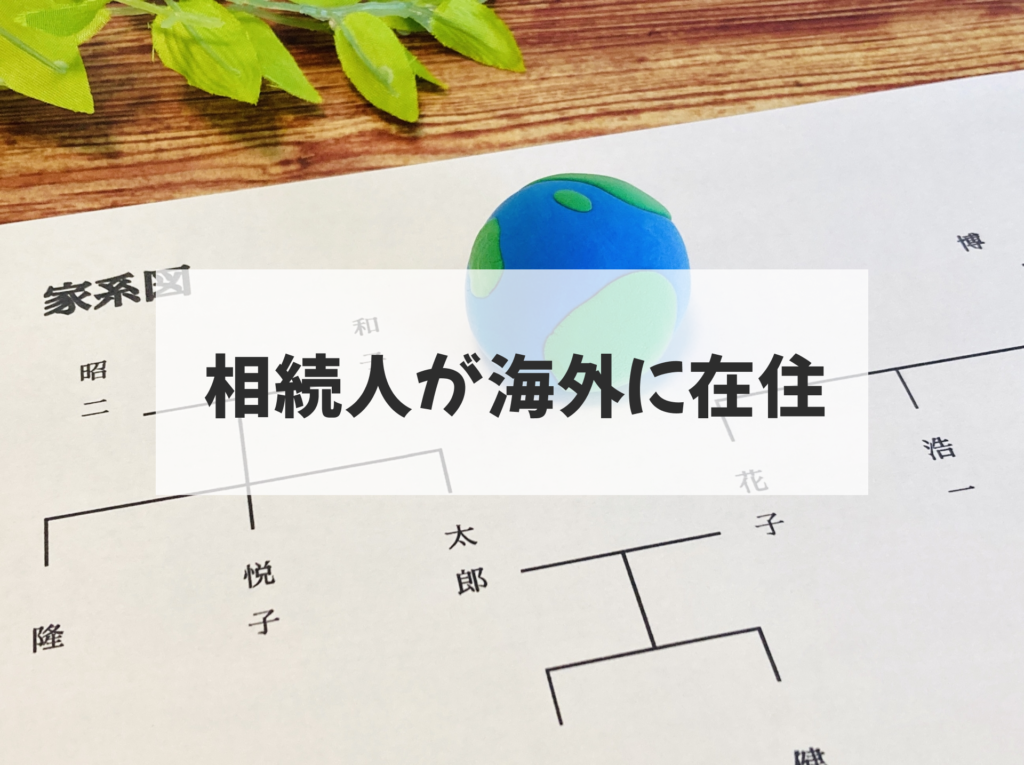
遺産相続は、原則として被相続人(亡くなられた方)の国籍がある国の法律が適用されます。
日本国籍の方が亡くなられた場合は、日本の相続法(民法)が適用されます。
しかし、例えば相続人となる子などが、海外に在住している場合はどうなるのでしょうか。
海外在住者は印鑑証明書が取得できない
国際結婚をされ、海外に永住している場合や、もしくはお仕事の関係で短期的に海外在住されている場合で、住民登録(住民票)を海外に移されている方は、
日本国内に住民票がないため、印鑑証明書が取得できません。
不動産の名義変更や銀行預金の解約など、各種の遺産相続手続きには、相続人の実印と印鑑証明書が必須となりますが、どうすればよいのでしょうか。

サイン証明書(署名証明)を取得する
日本国籍の方で、海外に在住しており、日本の印鑑証明書が取得できない方は、在住されている国の、日本大使館や領事館などで、サイン証明書(署名証明)を取得していただく必要があります。
参考:外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて
サイン証明書(署名証明)は2種類、貼付型と単独型
「形式1」(貼付型)
署名をする(実印を押印する)必要のある書類に、申請人が署名したことを証明する形式です。
遺産分割協議書や銀行の相続手続き書類などを、日本大使館や領事館などに持参し、領事の面前でサイン(署名)します。
持参した書類に、在外公館が発行する証明書が貼付されます。
「形式2」(単独型)
日本の印鑑証明書のように、申請人の署名および拇印であることの証明を、一枚の証明書として発行されます。
実際の遺産相続手続きでは、遺産分割協議書や銀行の相続手続き書類などにサイン(署名)、拇印を押印し、単独型のサイン証明書(署名証明)を添付し、使用ます。

参考:サイン(署名)証明申請書(在メルボルン日本国総領事館)
在留証明について
日本の住民票に代わる書類が、日本大使館などで発行される在留証明書です。
サイン証明とあわせて提出を求められるケースがございますので、必要なときは、大使館などで取得します。
サイン証明、在留証明、とも、本人が出向いて申請することが必要
海外に在住されている方は、お住いの地域を管轄する大使館などに、必ず本人が出向いて申請をしなくてはなりません。
本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが、対応は各地域の大使館などによって異なります。
大使館などが非常に遠い、お仕事の都合で時間が取れない、など、ご事情がおありと思いますが、なんとか時間を作ってご対応いただく必要がございます。

参考:在外公館における証明
相続人が外国籍のとき
相続人となる子などが、日本国籍から外国籍に転籍されたときは、サイン証明、在留証明とも、取得できません。
国籍を取得された国のルールに従って、各種の証明書を手配していく必要がございます。
発行された証明書が外国文字のときは翻訳が必要
たとえば海外で亡くなられた場合、死亡証明書が現地の文字で発行される場合があります。
相続人に関する証明書類も、外国文字の記載で発行された場合は、すべて日本語への翻訳が必要です。
誰が翻訳してもよいが、、
公的書類が翻訳されたとき、誰が翻訳をしたのかを、翻訳証明として、
本人や利害関係者ではない第三者が、客観的な立場で資料を厳密に正しく翻訳した旨の宣誓供述文を、翻訳者が記載します。
日本には、翻訳者について国家資格がありませんため、知人などに依頼しても問題ないケースもありますが、提出先によっては、公正証書にすることを求められるケースがございます。

参考:翻訳証明
翻訳証明書を公証役場で公証してもらう
翻訳証明書を公的なものにするためには、公証役場で認証の手続きをしてもらいます。
提出先に求められたら対応するしかありませんので、各機関と相談しながら、相続手続きの事務を進行していくことになります。