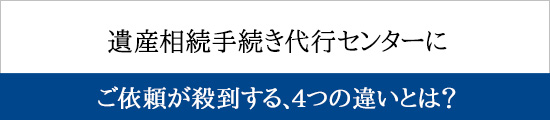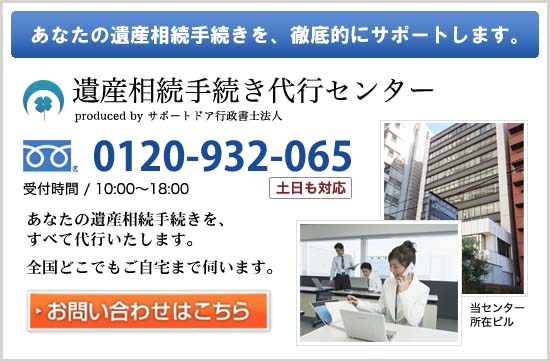たとえば、夫が亡くなり、妻と子供が相続人になる場合で、子が未成年、もしくは幼児だったとき、遺産相続の手続きはどのように進めれば良いのでしょうか?
このページでは、未成年者が相続人になるときの遺産相続手続きについて、詳しく説明しています。
未成年者が遺産相続でできないこと
未成年者は、単独で、遺産分割協議をおこなうことができません。
たとえ分割内容をきちんと理解し、合意したとしても、遺産分割協議書の未成年者のサインは無効になってしまいます。
これは、まだ判断能力が十分でない未成年者を、法律が保護するために、設けられた制限です。
未成年者の権利を保護するために法定代理人が定められる
一般的に、未成年者は、父母が親権者として子を保護し、
未成年者が何らかの法律行為(売買契約や賃貸借契約など)を行う場合は、親権者である父母が、子の法定代理人として、子の代わりに契約をしたりサインをしたりします。
未成年者が単独でおこなう法律行為は無効になりますため、子が勝手に父母の承諾なく、大きな買い物をした場合などは、父母があとから取り消すことができます。
遺産分割協議では、特別代理人が必要
子が法律行為をおこなうには、法定代理人が子の代わりになるのですが、
遺産分割協議においては、たとえば父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になるとき、母は、配偶者としての相続人の立場と、子の法定代理人としての立場となり、一人二役の立場になってしまいます。
相続人という立場では、母も子も対等の権利関係であるため、母が自分のためにする遺産分割協議と、母が法定代理人として子のためにする遺産分割協議と、真っ向から立場が対立してしまうため、利益相反行為(片方の利益になる一方で、他方の利益を損なう状況にある行為)となり、遺産分割協議が有効に成立しません。
そこで、遺産相続の実務では、一時的に、遺産分割協議のときだけ、未成年の子を大人が代理し、遺産分割協議書にサインをします。
この代理人を、特別代理人といい、子の住所地の家庭裁判所に申し立て、許可をもらい、就任します。
子の祖父母や、母の兄弟姉妹などに就任してもらうケースが多いです。
遺産分割が終了すれば、特別代理人としての任務も終了します。
親権者が相続人でなければ特別代理人は不要
たとえば父母が離婚していて、父が亡くなったとき、離婚している母は相続人ではなく、未成年の子だけが相続人となるときは、母と子の立場が利益相反関係にはなりませんので、母は子の法定代理人として、各種の遺産相続手続きを代理することができます。
未成年の子が複数人いるときは注意が必要
1人の親権者が子を代理できるのは、1人の子に対してのみです。
子が2人いるとき、母が上の子の法定代理人として代理するときは、母は下の子の代理人となることができません。
上の子と下の子の相続人としての権利が対立し、母が2人を代理すると利益相反となってしまうためです。
この場合も、やはり、母が上の子を代理するときは、下の子のために、特別代理人をつける必要がありますので注意してください。
銀行口座の解約には、特別代理人が不要なケースも多い
父が亡くなり母と未成年の子が相続人となるとき、亡くなった父の銀行口座を相続するには、相続人全員の署名捺印が必要ですが、実務では、母がすべて代理できるケースが多いです。
子が2人いても、母としての立場、上の子の代理人しての立場、そして下の子の代理人しての立場と、一人三役で手続き書類にサインをすることで、銀行口座が解約できる場合があります。
これは、母が親権者として子の預金を管理することができますので、手続きの簡便性を考慮し、配慮されたものと思われます。
ただし、これは各金融機関の個別判断のため、本来であれば特別代理人が必要です。
金融機関から特別代理人を求められたときは、特別代理人を選任しなくてはなりません。
不動産の名義変更には、特別代理人が必ず必要
父が亡くなり母と未成年の子が相続人となるとき、自宅が父の名義であれば、遺産相続として、自宅の名義を変更しなくてはなりません。
このときに、子が未成年であればなおさら、母の名義に変更されるケースが多いですが、そのためには、自宅の名義を母にすると記載した遺産分割協議書が必要になり、相続人である子もサインをしなくてはなりません。
未成年である子がサインをした遺産分割協議書は無効ですので、特別代理人を選任する必要があります。
不動産を共有にするときは、特別代理人が不要
自宅などの名義を、特定の1人の単独名義にせず、法定相続分通りに、未成年者にも共有させるときは、遺産分割協議書が不要ですので、特別代理人も不要で、名義を変更することができます。
民法改正で未成年は18才未満に
2022年、民法が改正され、成人になる年齢が20才から18才に引き下げられました。
これにより、高校生であっても、18才の誕生日を迎えたあとであれば、成人として、単独で、遺産分割協議がおこなえるようになりました。
父が亡くなったとき、子が15才や16才など、もうすぐ成人を迎える年齢であるならば、特別代理人を選任せず、子が18才の誕生日を迎えるのを待って、自宅の名義変更をおこなうことも、実務上は可能です。
ただし、相続登記は亡くなってから3年以内におこなわなくてはなりませんので、3年以内に子が成人しないときは、従来通り特別代理人を選任し、手続きをおこなう必要があります。