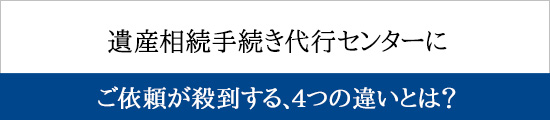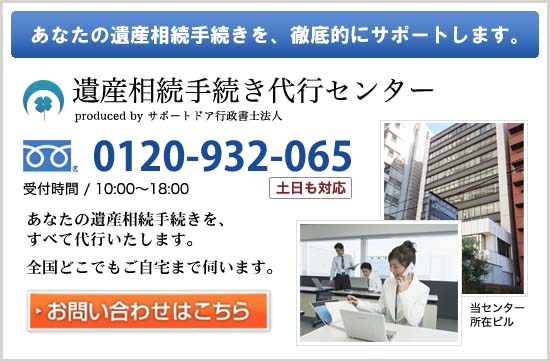相続人の間で公平に遺産を分けるために、寄与分という制度があります。
被相続人(亡くなった人)の財産を築くために、陰ながら支えたり、無償で手伝ったりした人は、そうでない人よりも、多く分割を受けることができる制度です。
被相続人の財産形成に寄与
- 被相続人の事業に関する労務の提供、
- 被相続人の事業に関する財産上の給付、
- 被相続人の療養看護、その他の方法により、
- 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者
寄与分について、上記のように規定されています。
ポイントは、被相続人の財産形成に寄与した、という点かとおもいます。
ただ単に、身の回りのお世話をした、介護をした、というだけでは、財産形成の寄与には当たりませんので、寄与分として認められることが難しくなっていました。
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人でないもの、例えばご長男のお嫁さんなどが、故人の身の回りのお世話や介護をしたときは、特別の寄与として、2019年の民法改正で、金銭請求が認められるようになりました。
なお、この方は相続人ではありませんので、従来の相続人(法定相続人)に対して、ご自身の特別の寄与分を請求することになります。
寄与分を決めることは難しい
相続人同士のお話し合いで、寄与分を認めるとしても、具体的な金額や配分等については、法律に規定がありません。
自分では相当、寄与したと思っていても、他の相続人はそうは思ってくれないかもしれません。
ここでお互いの言い分がかみ合わないときは、なかなか合意できないことになります。
家庭裁判所の調停
お互いが譲らず、納得がいかない時は、家庭裁判所で調停をします。
寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める
寄与分をもらう方にしてみれば、全遺産の半分か、それ以上をもらって当然と思うかもしれませんが、実際の判例では認められにくいようです。
30年から40年にわたって被相続人の家業を無償で手伝ったというケースでも、全遺産の1割から3割。
妻の方が稼ぎ頭で名義だけが夫になっていたケースでも、5割がやっとです。
夫が亡くなってから妻の貢献度を主張しても、他の人には残念ながら伝わりません。
生前に遺言を書いておいてもらうのが確実です。